【#3】不適合が発生したら:問題の絞り込みと問題の確定
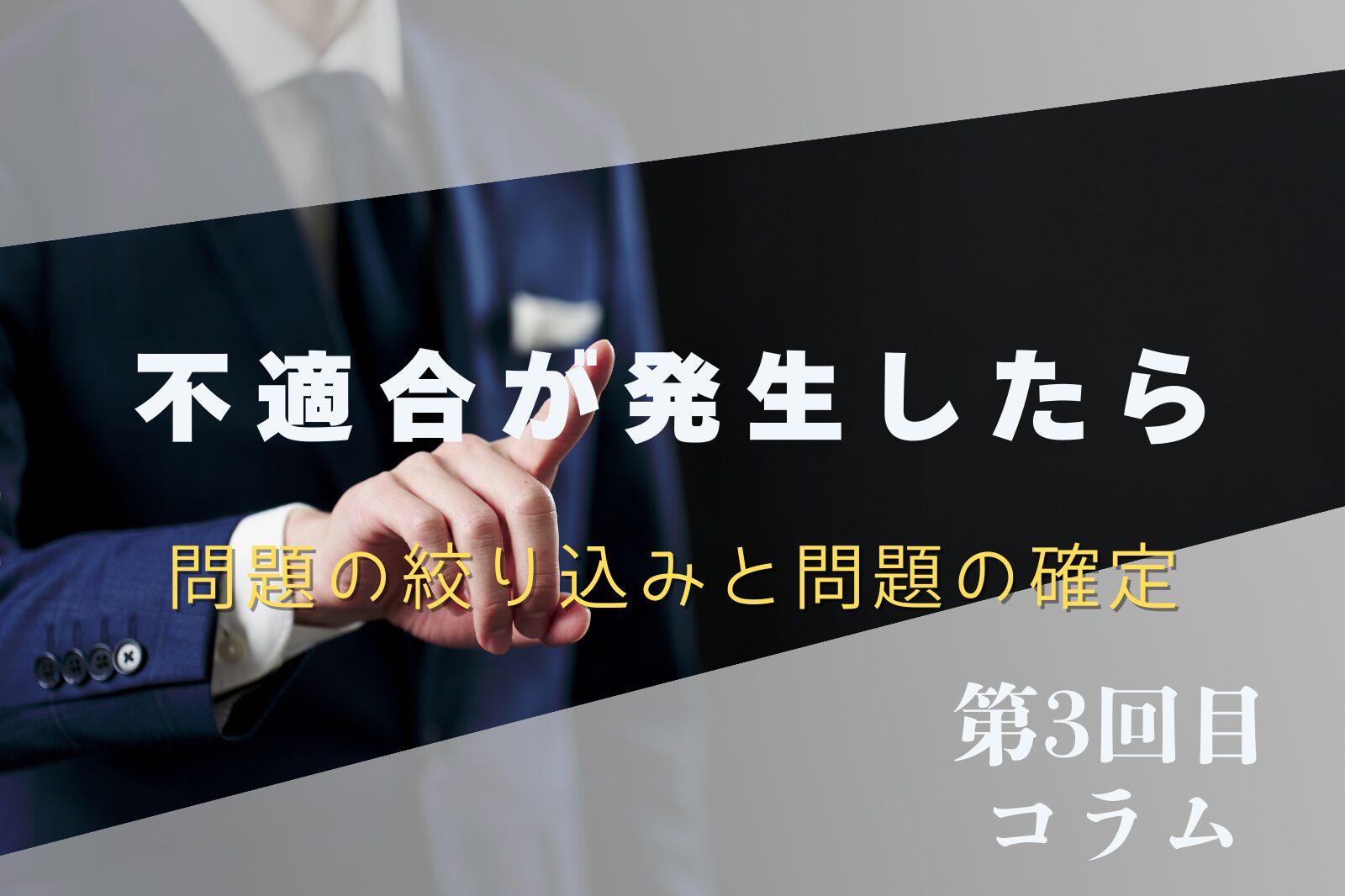
今回は、原因調査の手順について、3番目の「問題の絞り込み」、4番目の「問題の確定」について説明します。
(c)問題の絞り込み
・問題点、可能性のある要因を洗い出したら、今回不適合となって顕在化した原因を探るために事象の絞り込みをします。
・以下のポイントで協議します。
「なぜ発生したのか」 ⇒複数の原因が重なることで発生することもあります。
「なぜ不適合事象を発見できなかったのか」 ⇒確認する項目が抜けていなかったか。
「なぜ不適合の流出を防げなかったのか」 ⇒お客様の使用条件で発生するのに、その条件で確認していなかったのか。
(d)問題の確定
(ア)絞り込んだ問題点を確定する前の確認をします。
すべきことをしていなかった、すべきではないことを実施していた ということはないか。
- 途中からマニュアルの規定が変わったのに、作業者への配布忘れで古いマニュアルで作業していた。
- 治工具の定期検査をしておらず、治具がすり減っていた。
- 治具が、複数の部品を組合せて使用するものだが、一部ない状態で使用した。
(イ)直接的な原因をFTAにより究明したら、その原因を発生させた誘発要因、背後要因も洗い出すために、
なぜなぜ分析を使用すると判りやすいでしょう。
FTAで究明した原因を頂上事象として、なぜそのような事象となったかを調査します。
- 作業を教えてもらった時から、マニュアル通りではなかった、マニュアルを見て作業するように指導がなかった。職場の風土もマニュアルを見ずに作業することを黙認している。
- マニュアル通りでなくても、結果の見た目は変わりなく、早くできると思っていた。
- マニュアルの記載があいまいで、個人の判断で作業していた。
- 正しい治具がなく、有り合わせのものを使っている。
- 組み合わせて使用する治具だが、すべての部品に識別がなく、かつ組み合わせ状態の写真もなくて確認できない。
- 似た部品が複数あるが、識別が判り難い。
- 照明が暗い、作業場の配置が悪い。
- 長時間残業が続いている、作業を焦らされている、作業中断して緊急作業を突っ込まれた。
- 作業者のその作業における能力評価が十分でないのに、作業させていた。
(ウ)原因とした事象となったとき、不適合事象となるか、と逆方向で考えるのも有効です。
一つの原因だけを遡っても、不適合減少に必ずしも結びつかない時は、複合的な原因も考慮すべきです。
(エ)試験などで再現させることも原因の特定に有用です。
次回は原因調査の手順について、5番目の「全体像の確認」、6番目の「問題の分析」、7番目の「対策の設定」について説明します。
文責:大橋 義仁
