#3 飛行機の安全性を確保する方法についての豆知識シリーズ
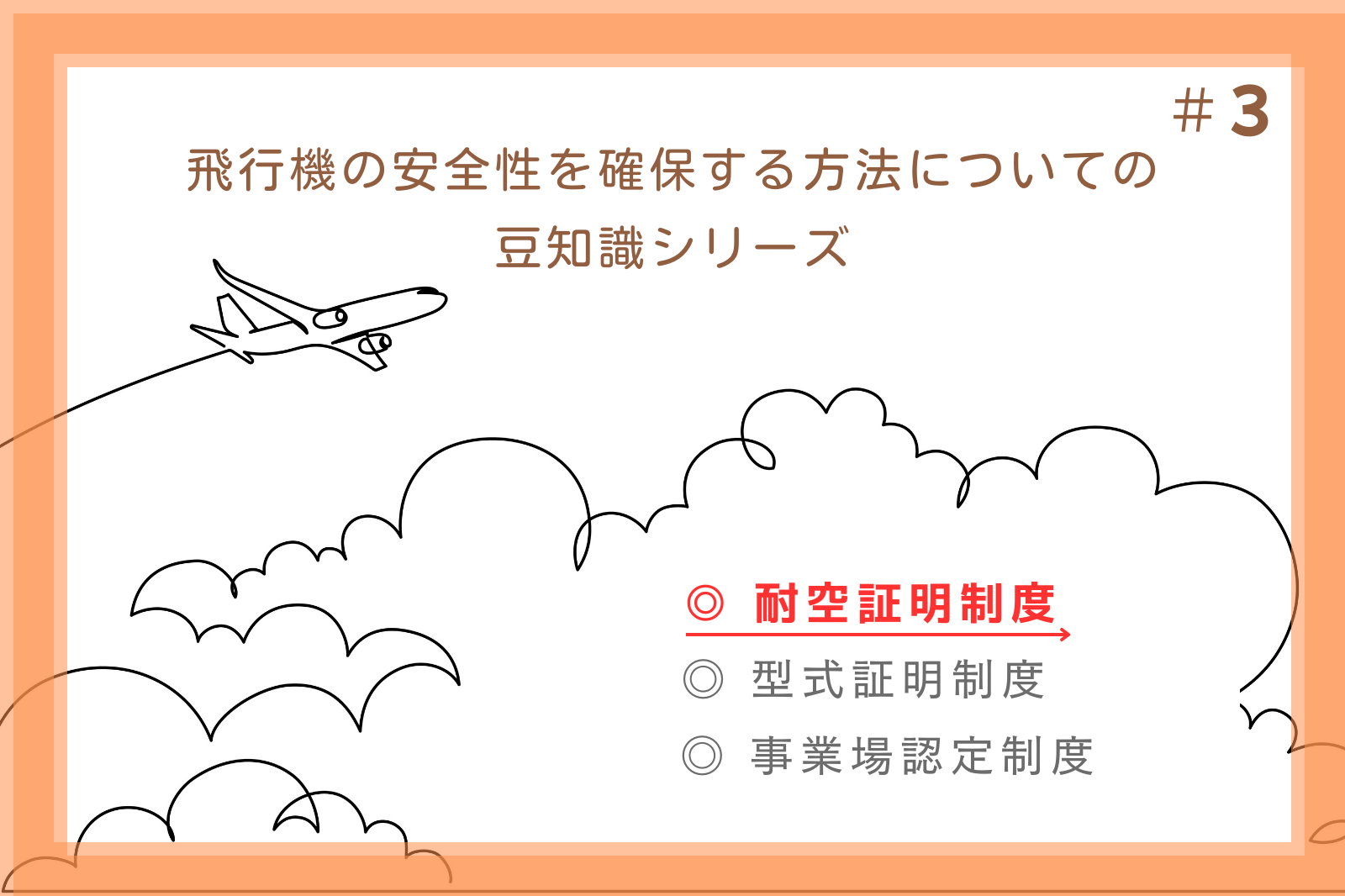
(1)耐空証明制度(航空機が安全性を確保していることを証明する制度)〔続き〕
前回は、「安全基準」について調べました。今回は、その「安全基準」を満たしているか(適合しているか)をどんな方法で確認しているかについて、調べましょう。
先ずは、誰が「安全基準」に適合していることを確認して安全性を確保していることを証明するかですが、それは国(航空局)です。実務を行うのは航空局の審査官・検査官です。
では、国内で設計されたり製造された航空機は、どの時点でどんな審査・検査をするのでしょうか。ちょっと脱線しますが、審査とか検査とかという言葉が出てきますが、設計に関する検査を審査と言う場合が多くあります。
どの時点でどんな審査・検査をするかについては、3つのポイントがあります。
①設計段階で設計で作成されたアウトプット(設計書、解析書、計算書、図面、技術仕様書、試験計画書などの設計者チームが点検・承認したもの)が「安全基準」に適合していることを審査・検査をして判定します。審査・検査を行う対象項目は、航空機の類別によって異なりますが、数百項目いやそれ以上の項目に及びます。
このことを、航空法上では“設計の検査”と言っています。
②製造の途中段階で、素材の受入れから加工・組立・社内検査及び引き渡しに至るまでの全ての工程を確定しており、それらが①の“設計の検査”で合格した図面や技術仕様書などの設計データに合致するものであること、及びそれらの工程で製造されたときの製造品が設計データからの逸脱を許容しないものであることを確認します。
このことを、航空法上では“製造過程の検査”と言っています。
③確定された工程で製造され社内検査が終えた段階で、その製造品が設計データに規定されている形状・構造・性能・機能などに合致していることを実地の立会いで確認します。
このことを、航空法上では“現状の検査”と言っています。
耐空証明 = ①設計の検査 + ②製造過程の検査 + ③現状の検査
と表現することができます。
航空機の安全を確保していることを証明する(耐空証明)ためには、航空機1機1機について①設計の検査と②製造過程の検査と③現状の検査を実施しなければなりません。
これでは、同じ設計・同じ製造方法の航空機を数多く生産するには、あまりにも多くの労力と時間を要して、あまりにも非現実的であり、無駄でもあります。そこで、考え出された方法に“型式証明制度”という制度があります。
次回は、“型式証明制度”について、調べてみましょう。
文責:田中 僅二
