#2 飛行機の安全性を確保する方法についての豆知識シリーズ
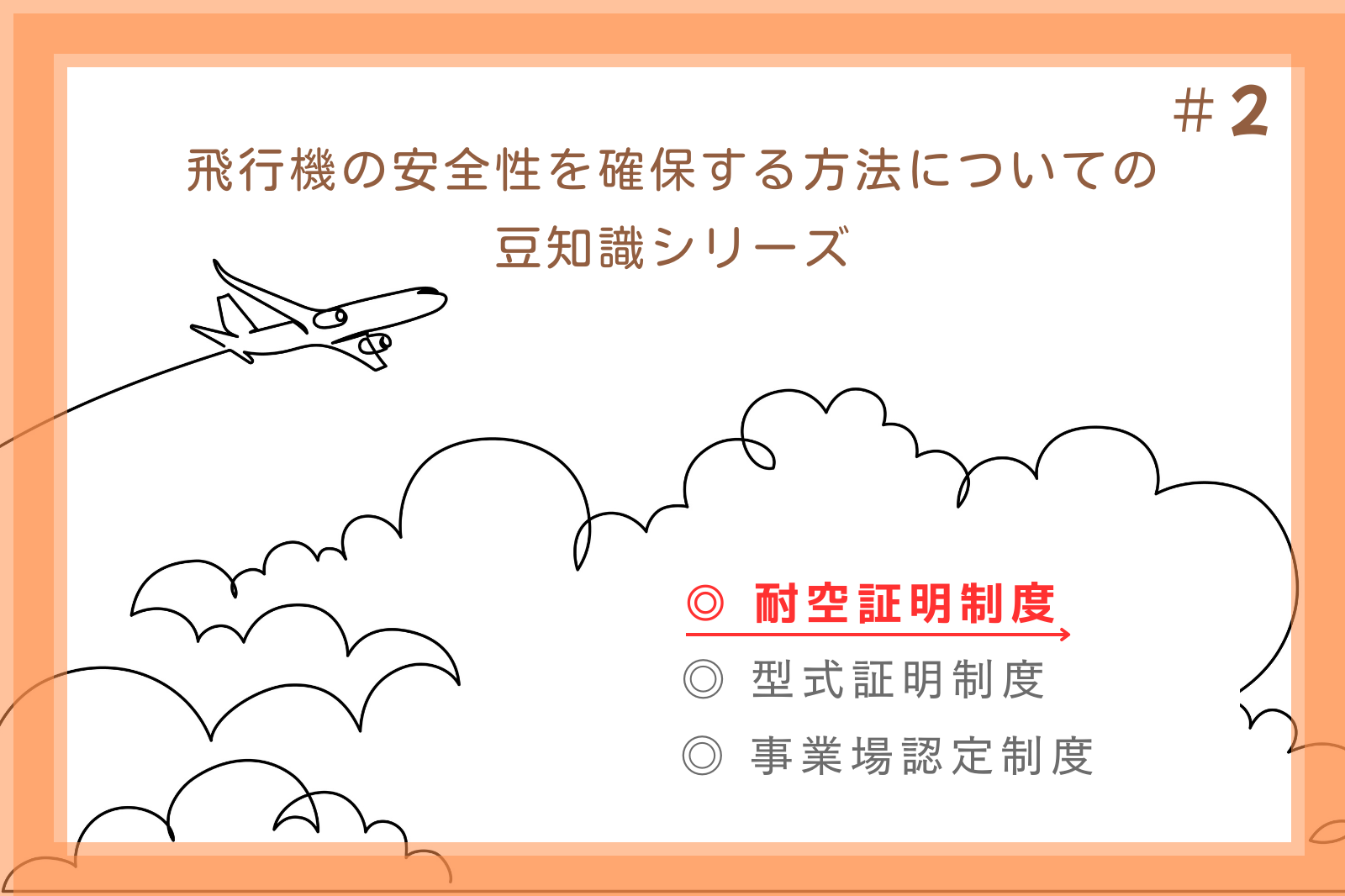
(1)耐空証明制度(航空機が安全性を確保していることを証明する制度)
1903年にライト兄弟がエンジン付き飛行機「フライヤー1号」で12秒間37メートルを飛ぶことに成功して以来、大気中をより長い時間飛ぼう、より高く飛ぼうと多くの技術者が挑戦してきました。
そして、数多くの失敗、事故を経験しながら、失敗・事故の原因を探求して、改良に改良を重ねて、航空機は進化し続けて、旅客機と称して、多くのお客様を乗せて世界のいろいろな国に運んでくれるようになり、安全で快適な乗り物となりました。
航空機の安全で快適な運航には、運航会社(エアライン)の適切な整備・運航体制の維持が欠かせないことはもちろんのこと、更にその前提として航空機自体が安全に飛行できるように設計され製造されていることが非常に重要なことであり、安全を確保している航空機であることを証明する必要があります。
この安全性を確保していることを、1機1機の航空機について証明する制度を“耐空証明”と言っています。
どのようにして証明していくのでしょうか⁈
まずは、こういう状態なら安全ですという基準が必要です。
その基準は、
①航空機及び装備品等の安全性を確保するための強度及び性能についての基準
②航空機の騒音の基準
③航空機の発動機の排出物(二酸化炭素を除く)の基準
④航空機の発動機の排出物(二酸化炭素に限る)の基準
というものがあります。航空法施行規則の附属書第一、第二、第三、第四に定められています。
特に、①の基準を定めている航空法施行規則の附属書第一の基準の記述だけでは判断しずらい事項が多くあることから、より具体的に記述したものに耐空性審査要領というものがあります。
例えば、
火災防止について、航空法施行規則の附属書第一では「航空機は、飛行中又は地上における火災の発生を、できる限り少なくするように設計しなければならない」と定めていますが、具体性に乏しいので、耐空性審査要領では「消火器の数、消火剤の種類、使用材料の耐火試験の方法、煙検知装置・火災発見器等の要件」が定められています。
なお、上記に示した基準のち、①のことを「安全基準」、②~④のことを「環境適合性基準」という場合と、 ①~④全てを「安全基準」という場合があります。
次回は、今回示した「安全基準」を満たしているか(適合しているか)をどんな方法で確認しているかについて、紹介します。
文責:田中 僅二
