#1 飛行機の安全性を確保する方法についての豆知識シリーズ
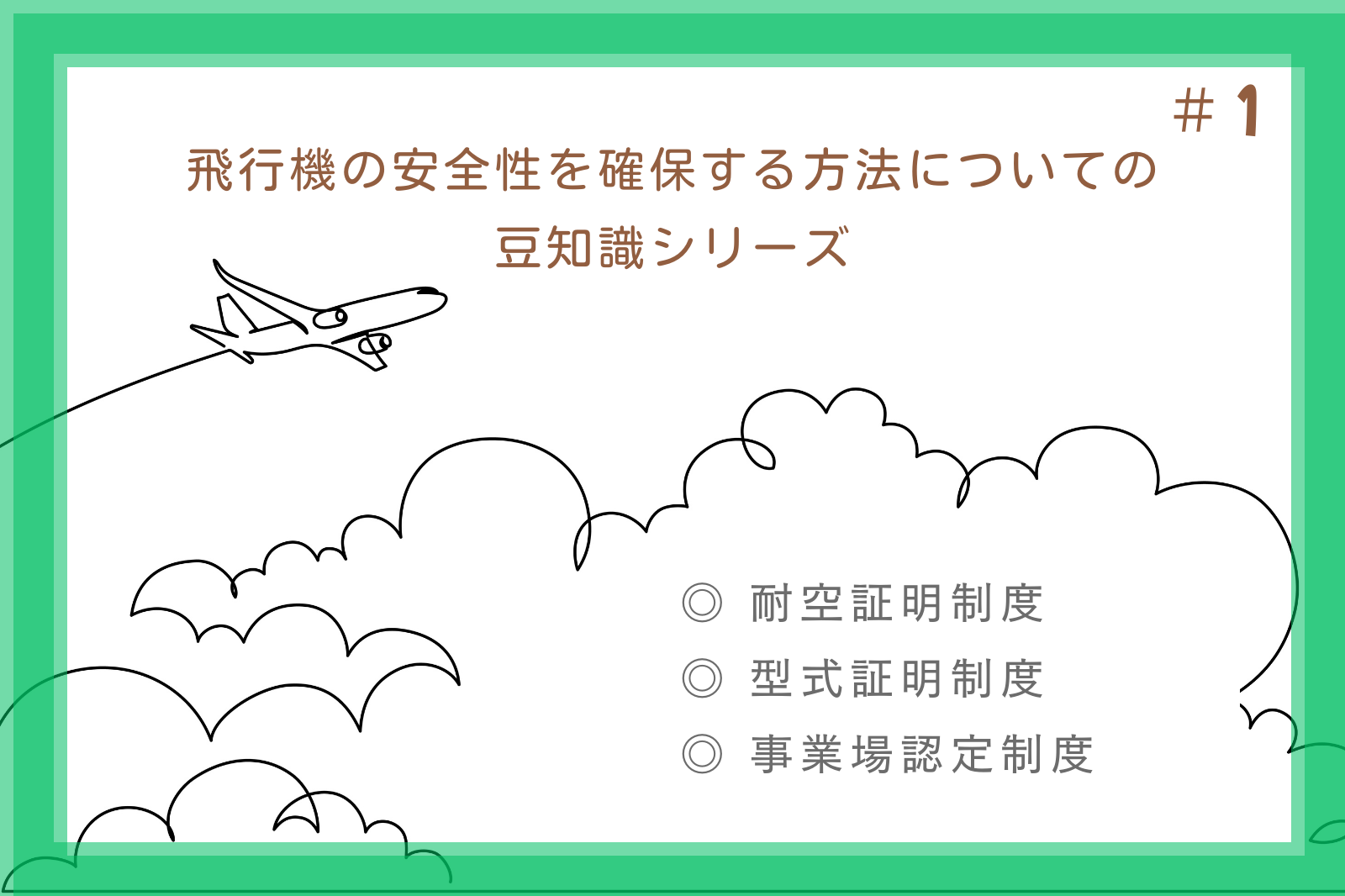
“空飛ぶクルマ”どうして“空飛ぶ車”と表記しないの⁈
“国産航空機 型式証明で難航、事業化が厳しく残念⁈
等々 日々の“空飛ぶ乗りもの”に関連するニュースが伝えられて、「あ~、そうか」となんとなく納得してそれっきりにしていることはありませんか?
“空飛ぶ乗りもの”について、少し深掘りして知識を広げてみませんか。
特に、“空飛ぶ乗りもの”の安全性をどのように確保しているかについて少し深掘りしてみましょう。
航空機とは、「大気中を飛行する機械」のことを言います。
“空飛ぶクルマ”も「大気中を飛行する機械」ですので、航空機のひとつの種類であるとされています。“車”は路上を走行するものですので、SF作品や未来予想図の世界で大空を自由に移動できるものを“空飛ぶクルマ”と言われていることから“車”でなく“クルマ”と表記しています。
この豆知識では、“空飛ぶクルマ”を含めて少し深掘りしてみます。
日本の国内で航空機を設計したり、製造したり、飛ばしたりするには航空法という法律が適用されます。
この航空法の定義では、「航空機とは、航空の用に供することができる機器」となっています。
航空法では、安全性を確保するために、航空法や航空法施行規則といった法令でいろいろな制度や基準が設けられています。
この豆知識では、
(1) 耐空証明制度
(2) 型式証明制度
(3) 業場認定制度
などについて、少し深掘りします。
次回のマガジンで、(1)の耐空証明制度について、調査しましょう。
文責:田中 僅二
